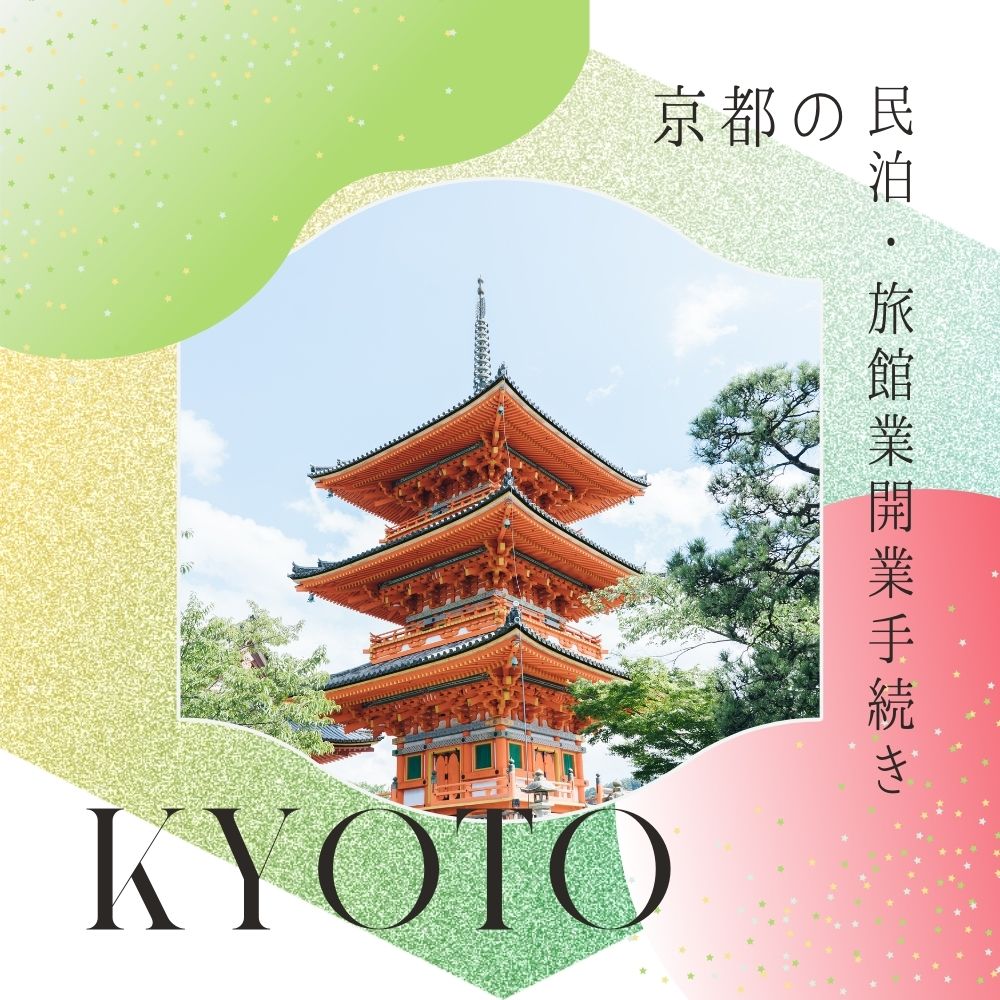この記事に辿り着いたということは、『これから民泊を始めたいが何から始めればいいのか分からない』と考えているのではないでしょうか?
私は京都市を中心に関西全域で旅館業や住宅宿泊事業など、いわゆる民泊を開業する為の手続きを代行している行政書士です。
この記事では、これから京都府で民泊を始めたい!という方に向けて開業までにしておくべきことをまとめました。
京都は他の地域比較しても厳しい独自の規制がありますので予め頭に入れておきましょう。
この記事を読んでいただくだけで最低限の知識を得ることは可能です。
いい物件を貸し出せば儲かるんでしょ?
そんな生半可な気持ちでやるのであればお勧めはできません。
京都は日本有数の観光都市でもあり、自治体の規制も厳しく競合他社も多数存在します。
また、民泊新法については法改正のスピードも速く、知らないことは自分自身に大きなデメリットをもたらします。
逆に知識を持っているだけであなたにとって大きなメリットとなります。
あなたがビジネスとして収益を上げていきたいのであれば、最低限の知識は自分で頭に入れておきましょう。
最低限の知識を学んだうえで、自分で手続きを進める時間がないのであれば、弊所は喜んでお手伝いさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
LINE:相談無料↓↓↓↓

それでは一緒に勉強していきましょう。

京都府で民泊を開業する際のスケジュールと手続きの流れ
まずはざっくりとでいいので民泊を開業する為の手続きの流れとスケジュールを把握しておこう。
湯水のごとく投資資金がある方は気にしなくてもいいが、ほとんどの場合はそうではない。
むしろ、初期投資をできるだけ節約するのはこれから経営を始めていく上で必要なことだ。
スケジュールを把握して逆算して物件を用意しよう。
①営業形態の選定
②物件の選定
③資金調達
④リフォーム&リノベーション
⑤必要な許認可の取得
⑥営業開始
上記のような流れが一般的なものとなる。
それでは詳細を説明していこう。

①営業形態の選定|旅館業or民泊新法?
いわゆる民泊を開業するには3つの営業方法があります。
・特区民泊(許可難易度は簡単。宿泊制限は無し。2泊~宿泊可能)
・民泊新法(許可難易度は簡単。年間最大180日。1泊~宿泊可能)
・旅館業法 (許可難易度は高難易度。制限なし)
上記の3つです。
簡単に違いを説明すると以下のようになります。
こう見ると特区民泊は魅力的ですよね。
しかし、京都府では現在特区民泊の申請はできません。
民泊新法による届出か旅館業法に基づく簡易宿所営業しか選択肢がないわけですね。
自分にはどの許可が必要になるのか?判断するポイントも簡単に説明しておきましょう。
下記は旅館業法と民泊新法の制度の違いです。(※京都市:京都市内において、いわゆる「民泊」の実施を検討されている方へより引用)

①営業場所
民泊を始める物件の用途地域や前面道路の幅。
旅館業法の方が比較的厳しい要件になっている。
②住居利用の有無
旅館業法については住居としての利用は不可。
③費用
許可の手数料だけでも旅館業法は52,800円。民泊新法は0円。
行政書士などの専門家へ依頼する場合も旅館業法の報酬の方が10万~20万円程度高額となる。
また、旅館業法の場合はバリアフリー条例が適用されるため工事費用などで高額になりやすい。
逆に民泊新法については家主不在型の場合は、管理を住宅管理事業者へ委託しなければならない。
④収益
旅館業法についてはほぼ宿泊制限はないが、民泊新法による届出の場合は年間180日までと営業日数が半分となる。
収益と原価を計算し、民泊にしようとしている物件での収益目標を達成できるのかを事前に検討しなければならない。
※民泊新法については下記記事も併せてお読みください。
②物件の選定
次に考えるのはメインとなる物件の選定です。
一番ワクワクするところですよね。
自分の色を思う存分に発揮することができます。
既に自分の所有している物件を使用するのか、新たに物件を買い取る又は借り入れて使用するのか。
選定する為の見るべきポイントを簡単に説明していきます。
・物件の場所
旅館業法の場合
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域 及び第2種中高層住居専用地域は建築NG
民泊新法の場合
基本NGはないが京都市は独自ルールとして、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域 及び第2種中高層住居専用地域は※3/16正午〜翌年1/15正午の間は営業不可。
・物件の構造
旅館業法の場合
客室面積:延床面積33㎡以上 (定員10人未満では定員×3.3㎡以上)
寝室面積:1 寝台を用いる場合 1人当たり3㎡以上
2 階層式寝台を用いる場合 1人当たり2.25㎡以上
3 布団を用いる場合 1人当たり2.5㎡以上
フロント:必要
バリアフリー条例適用
民泊新法の場合
客室面積:宿泊者が占有する面積が定員×3.3㎡以上
フロント:不必要
バリアフリー条例適用無し
※バリアフリー条例について R6.11.8_barizyorei.pdf
・近隣住民への説明会
京都では旅館業及び民泊新法ともに近隣住民への説明が必要となります。
以下は例です。
・駆けつけ要件
京都市は全国でもかなり厳しい駆けつけ要件が定められています。
物件から徒歩10分。800m以内に対応できる人材を置かなければなりません。
詳しくは下記記事をお読みください。
③資金調達
民泊を始める際に必要な開業資金を用意するのに金融機関からの融資が必要となる場合があります。
間違っても利息の高いサラ金から借りるのはやめてくださいね。
また、自己資金でギリギリまかなえそうでも現金はあるにこしたことはないのと、今後ビジネスを続けていく為にも金融機関へ提出する事業計画を考えることは有益な経験となります。
公庫・地銀・信用金庫など。
個人的には公庫は許可を取得している物件を買い取るなどでなければ厳しい印象です。
必要であれば、融資に強い税理士などの紹介もしていますのでお気軽にお問い合わせください。
④リフォーム&リノベーション
旅館業法や民泊新法に合わせて工事を行うことは勿論ですが、気を付けるのは消防設備についてです。
宿泊者の安全を守ることは、民泊運営において最も重要な責務です。消防設備の設置は法令で義務付けられており、安全対策を怠ると重大な事故につながる可能性があります。そのため、適切な消防設備の設置と定期的な点検・メンテナンスは必須事項ですね。
細かい説明は省きますが、細かく定められていますので事前にご相談下さい。
また、リフォームを行う際にターゲットとする顧客をイメージしてみてください。
例えば外国人をメインの顧客で考えている場合は、外国人の好むテイストであったり、予想される体格を考えて少し大きめのトイレやシャワーを用意し、生活を快適に過ごせるように配慮したり。
⑤必要な許認可の取得
①で考えた必要な許可を取得しましょう。
京都では旅館業法or民泊新法。
予想の許可までのスケジュールは下記のようになります。
・旅館業法に基づく簡易宿泊
1.事前相談
2.計画の公開(標識の掲示,近隣住民及び自治会等への説明)
3.許可申請 (標準処理期間は30日)
4.実地調査
5.許可書交付
1~5までで3~6カ月程度となります。
旅館業許可は申請する人の経験値によっても大きく差が出る許認可の為、安いだけではなくある程度経験のある行政書士に依頼する方がトータルでは安くなります。
・民泊新法(住宅宿泊事業法に基づく届出)
1.事前相談
2.計画の公開(標識の掲示,近隣住民及び自治会等への説明)
3.許可申請 (標準処理期間は30日)
4.実地調査
5.標識発行
事前相談から、周辺住民への説明・事業計画の掲示などを経て、届出書を提出するまではおおむね2箇月程度、施設(届出住宅)の現地調査を経て、届出を受理し、法令に定める標識を発行するまでは1箇月半程度が手続に要する標準的な期間となっています。
⑥営業開始
民泊に必要な許認可が取得できれば、あなたも経営者となります。
広告の為の写真撮影や広告の原稿打ち合わせ。アメニティの充実や管理業者との打ち合わせなど、まだまだやる事は山積みです。
一つ一つ確実にこなしていくことであなたの経営者としてのキャリアも上積みされていきます。
楽しいことばかりではありませんが、あなたが経営に集中できるよう微力ながらサポートさせていただきます。
民泊開業サポーター
最後までお読みいただきありがとうございます。
如何でしょうか?
少しは開業へのイメージはできましたか?
弊所は開業より民泊の手続きをメイン業務として行ってきました。
京都での開業の際にはぜひ一度ご相談してください。
旅館業許可・民泊の許可でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
下記の問い合わせフォームに必要事項をご記入いただくか、お電話・メールでの問い合わせを受け付けています。