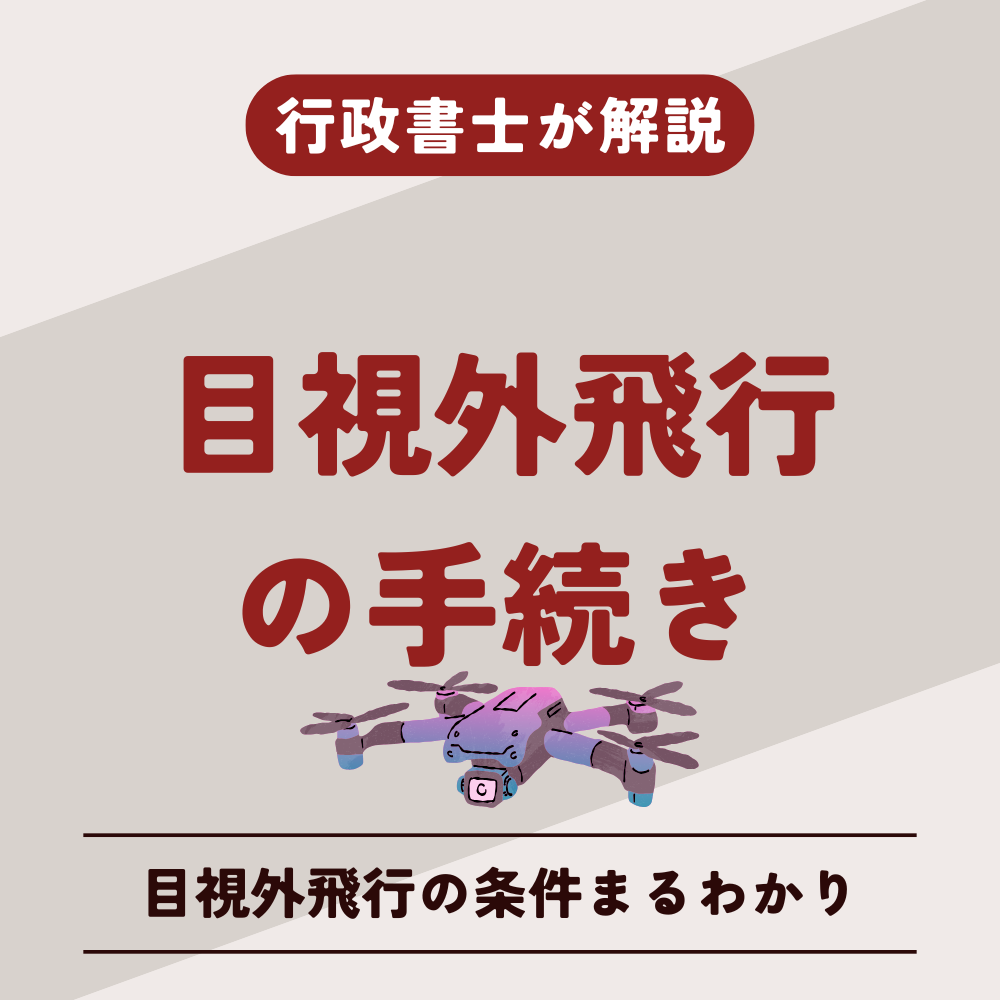皆さんご存じの通り、100g以上のドローン(無人航空機)は【航空法】の規制対象となり、一定の条件下で飛行させるには飛行許可承認が必要となります。
その一つが【目視外飛行】です。
目視外飛行は、ドローンを飛行させる方であれば切っても切り離せない飛行方法といっても過言ではありませんよね。
この記事では、ドローンを操縦する上で必須となる【目視外飛行】の定義と飛行許可承認申請方法について解説させていただきます。
お忙しい方の為に3分程度で読めるよう、要点をギュッとまとめましたので最後までお読みください。
目視外飛行の定義
まずは目視外飛行とはどんな飛行方法なのか、認識を共有しておきましょう。
根拠法
(飛行の方法)
第百三十二条の八十六 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。
一 日出から日没までの間において飛行させること。
二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
簡単に言うと、要するに目の届く範囲で操縦しましょう!ということですよね。
・・・これで終わるとわざわざ解説する意味がありません。。。
まぁ条文の通りなんですが、あいまいな書き方なんでこれだけだと読む人によって解釈の仕方が別れる可能性があります。
条文はだいたいそんな作りなんですが、そのあいまいさを補完する為に航空局が解釈の説明をしてくれていますので、この機会に読んでおいてください。
無人航空機に係る規制の運用における解釈について(001303820.pdf )
上記の資料の中でこのような記述があります。
「目視」とは、操縦者本人が自分の目で見ることをいうものとする。
このため、補助者による目視は該当せず、また、飛行状況を専らモニターを用いて見ることまた双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」にはあたらない。
なお、安全な飛行を行うためにバッテリー残量を確認する目的等で無人航空機から一時的に目を離し、モニターを確認する等は目視飛行の範囲内とする。
簡単にまとめると、、、
目視外飛行に該当する飛行方法
・補助者だけの目視
・プロポやFPVゴーグルの映像を見ながらの飛行
ということは、本当に自分の目で直接見える範囲でのみの飛行ですね。
その人の視力や諸条件によって変わりますが、平地であれば100m~300m程度。山などで飛ばす場合は、木などの障害物に視界が阻まれる可能性が高いのでもっと短くなる可能性がありますので注意が必要です。

目視外飛行には許可申請が原則必要
原則として、目視外飛行をする場合にはDIPS2.0で飛行許可申請をする必要があります。(書面でもできますが基本オンラインでしょう)
機体・操縦者・安全確保体制に関する一般基準に加えて、機体・操縦者・安全確保体制について追加基準が定められていますので解説していきますね。
許可を得ずに飛行させてしまうと、なんと50万円以下の罰金ですし、しっかりと許可を取得することを忘れないでくださいね。
それでは早速申請の条件を確認していきましょう。
目視外飛行を大きく分別すると下記の4つになります。
①『無人地帯で補助者を配置する目視外飛行』
②『無人地帯で補助者を配置しない目視外飛行』
③『有人地帯で補助者を配置する目視外飛行』
④『有人地帯で補助者を配置しない目視外飛行』
それでは解説していきますね。
①『無人地帯で補助者を配置する目視外飛行』
目視外飛行などの特定の飛行形態は、『機体』『操縦技量』『安全確保のための体制』の3つの追加適応基準というものが定められています。
『機体の基準』
・自動操縦システムを装備し、機体のカメラ等で機外の様子を監視できること。
・地上において無人航空機の位置・異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む。)。
・電波断絶等の不具合発生時に危機回避機能※が正常に作動すること。
※自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等のフェールセーフ機能。
『操縦技量』
・モニターを見ながら、遠隔操作により、意図した飛行経路を維持しながら飛行でき、経路周辺において安全に着陸できること。
・必要な能力を有していない場合には、関係者の管理下にあって第三者が入らないように措置された場所において目視外飛行の訓練を行うこと。
『安全確保のための体制』
・飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。
・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
『目視外飛行の包括申請は可能』
目視外飛行は包括申請可能です。
申請の際は標準マニュアル02を使用しましょう。
よくある勘違いで、『夜間飛行』+『目視外飛行』も包括申請で大丈夫と思われている方がいらっしゃいますが、この場合は個別申請が必要です。
標準マニュアル02の「安全を確保するために必要な体制 」に「夜間の目視外飛行は行わない。 」と記載があります。
②『無人地帯で補助者を配置しない目視外飛行』
無人地帯・補助者無し・目視外ということは、レベル3飛行ですね。
目視外飛行を補助者無しで行うためには、補助者の役割を機体や地上設備等で代替する必要があります。
上記の補助者有りの場合の追加適応基準に下記の要件が追加されます。
『機体の基準』
・航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備すること又は飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと。
・機体や地上に設置されたカメラ等により飛行経路全体の航空機の状況を常に確認できること。
・第三者に危害を加えないことを製造者等が証明した機能を有すること。
・地上において、無人航空機の針路、姿勢、高度、速度及び周辺の気象状況等を把握できること。
無人航空機周辺の気象状況等の把握の例
※無人航空機の制御計算機等で気象諸元を計測又は算出している場合はその状況を操縦装置等に表示する。
※飛行経路周辺の地上に気象プローブ等を設置し、その状況を操縦装置等に
表示する等
・想定される運用により、十分な飛行実績を有すること。
『操縦技量』
・モニターを見ながら、遠隔操作により、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること及び飛行経路周辺において無人航空機を安全に着陸させることができること。
・遠隔からの異常状態の把握、状況に応じた適切な判断及びこれに基づく操作等に関し座学・実技による教育訓練を少なくとも10時間以上受けていること。
・必要な能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所において、目視外飛行の訓練を実施すること。
『安全確保のための体制』
・飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。
・飛行経路には第三者が存在する可能性が低い場所※を設定すること。
・全ての飛行経路において飛行中に不測の事態が発生した場合に、付近の適切な場所に安全に着陸させる等の緊急時の実施手順を定めるとともに、第三者及び物件に危害を与えずに着陸ができる場所を予め選定すること。
・飛行範囲の外周から製造者等が保証した落下距離の範囲内を立入管理区画として設定すること。
・立入管理区画を設定した場合は、当該立入管理区画に立看板等を設置するとともに、インターネットやポスター等により、問い合わせ先を明示した上で上空を無人航空機が飛行することを第三者に対して周知するなど、当該立入管理区画の性質に応じて、飛行中に第三者が立ち入らないための対策を行うこと。
無人地帯で補助者を配置しない目視外飛行は包括申請NG
包括申請はNGですので個別申請をする必要があります。
③『有人地帯で補助者を配置する目視外飛行』
飛行マニュアル02にあるように原則として飛行禁止。
人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。
ただし、業務上、やむを得ず飛行が必要な場合は、常時操縦者と連絡を取り合うことができる補助者の配置を必須とし、飛行範囲を限定して不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
④『有人地帯で補助者を配置しない目視外飛行』
レベル4飛行と言われる飛行方法ですね。
こちらが実現すれば、ドローンでの配送など、様々な分野でドローンが活躍する未来が現実的になります。
条件は厳しいですが、、、
機体の条件
①機体認証
第一種型式認証
第一種機体認証
②操縦者の条件
一等無人航空機操縦士の技能証明+目視外の限定解除
細かいことを言うとまだまだありますが、現状まだまだ対応機種が少ないのと事例も少ないため、許可申請の際には細かく調整していく必要があります。

ドローン専門行政書士が代行します
いかがでしょうか?
今回は目視外飛行についてまとめました。
包括申請であればご自身でも全然申請可能ですが、レベル3飛行以上の個別申請は非常に手間です。
時間が余裕があるのであればご自身で申請してみるのも勉強になりますが、「いつまでに」という期限のある場合は私達行政書士を頼ってください。
弊所はドローンの飛行許可申請に特化しており、ご相談お見積りは無料です。
全国最安値ではないかもしれませんが、可能な限り予算に合わせて動かせていただきますのでお気軽にご相談ください。
包括申請 19,800円(税込)
個別申請 33,000円(税込)~
機体登録 5,500円(税込)~
下記の問い合わせフォームに必要事項をご記入いただくか、お電話・メールでの問い合わせを受け付けています。